引きこもり相談

一人で抱え込まないために、医療につながる第一歩
「朝起きるのがつらい」「外に出るのが怖い」「気がついたら家にこもる生活が続いている」―こうした状態を「引きこもり」と表現します。内閣府の調査では、15〜64歳の人口のうち推計約146万人が引きこもり状態にあるとされ、決して珍しいことではありません。 引きこもりは本人にとっても、ご家族にとっても大きな悩みの種となります。「怠けているだけではないか」と誤解されることもありますが、実際にはうつ病や不安障害、発達障害、適応障害など、精神疾患が背景にあることも少なくありません。放っておくと状態が長期化し、就学や就労の機会を失ったり、社会とのつながりがますます希薄になったりすることもあります。 そのため、早い段階での相談や支援がとても大切です。本記事では、引きこもり相談の意味や流れ、相談できる場所についてわかりやすく解説します。

引きこもりとは?
「引きこもり」とは、6か月以上にわたり家庭にとどまり、学校や職場に行かず、外出もほとんどしない状態を指します。背景にはさまざまな要因があります。たとえば、不登校や職場でのストレスをきっかけに外に出られなくなるケース、もともとの対人不安や発達特性が強く表れるケース、あるいは精神疾患による気分の落ち込みや意欲低下が影響している場合もあります。大切なのは「引きこもりは一人の性格の問題ではなく、さまざまな要因が重なって生じる状態」であるという理解です。本人が自分を責めてしまうことも多いため、周囲が正しく理解することが回復への第一歩になります。
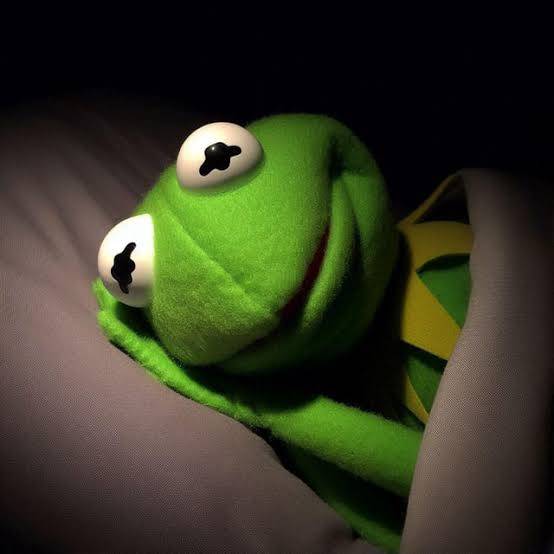
ご本人が抱える悩み
引きこもり状態にある方は、「外に出なければいけない」とわかっていても、強い不安や恐怖心が邪魔をして行動できないことが多くあります。夜型の生活リズムが固定して昼夜逆転になってしまったり、周囲との接触を避けるあまり孤独感が強くなったりすることもあります。「自分はダメな人間だ」と否定的に考えてしまい、ますます社会から距離を置くようになることも少なくありません。この悪循環が続くと、回復までの道のりがさらに長くなってしまうため、早めに支援につながることが重要です。

ご家族が抱える悩み
引きこもりは本人だけでなく、ご家族にとっても大きな負担です。「声をかけても返事がない」「将来どうなってしまうのか不安」といった悩みを抱える親御さんは多くいます。また、「どう接していいかわからない」「専門機関に相談すべきか迷う」という戸惑いの声もよく聞かれます。ご家族だけで支えようとすると、つい「早く外に出なさい」と強く言ってしまい、その結果、家庭内暴力に発展したり、逆に遠慮して声をかけられなくなったりすることもあります。いずれも悪循環になりやすいため、第三者に相談しながら適切な距離感を保つことが大切です。

相談の第一歩
「どこに相談すればいいのかわからない」と感じる方は少なくありません。引きこもり相談の窓口は複数あります。自治体の相談センター、教育機関、就労支援施設、そして医療機関です。なかでも精神科クリニックは、うつ病や統合失調症、不安障害、発達障害など医療的な背景があるかどうかを判断し、必要な治療や支援につなげる役割を担います。診断書が必要な場合や、休学・休職の手続きを伴う場合にも医療機関が関与することが多いため、早めに相談しておくと安心です。
当院での引きこもり相談の流れ
1 ご家族・ご本人からのお問い合わせ
2 初回面談
3 医師による評価
4 支援方法のご提案
5 継続的なフォロー
まとめ

引きこもりは本人だけの努力で解決できるものではなく、社会的な支援や医療の関与が大切になります。長期化することも多く、自然回復だけに任せず、本人もご家族も一人だけで悩まず、早めにご相談ください。 当院では、精神科クリニックとしての診療と並行して、引きこもりに関するご相談を受け付けています。「相談してもいいのだろうか」と迷っている段階でも構いません。まずはお気軽にお問い合わせください。
