認知症について
認知症というと、「高齢になると誰でもなる病気」「物忘れがひどくなる病気」といったイメージを持たれる方が多いかもしれません。 しかし実際には、加齢だけが原因ではなく、脳の神経細胞の障害によって起こるさまざまな症状の総称です。 日本では65歳以上の約7人に1人が認知症を有しているとされており、年々患者数は増加しています。 また、早期に適切な対応や治療、生活支援を行うことで、進行を緩やかにしたり、症状を軽減することが可能なケースもあります。
認知症とは?
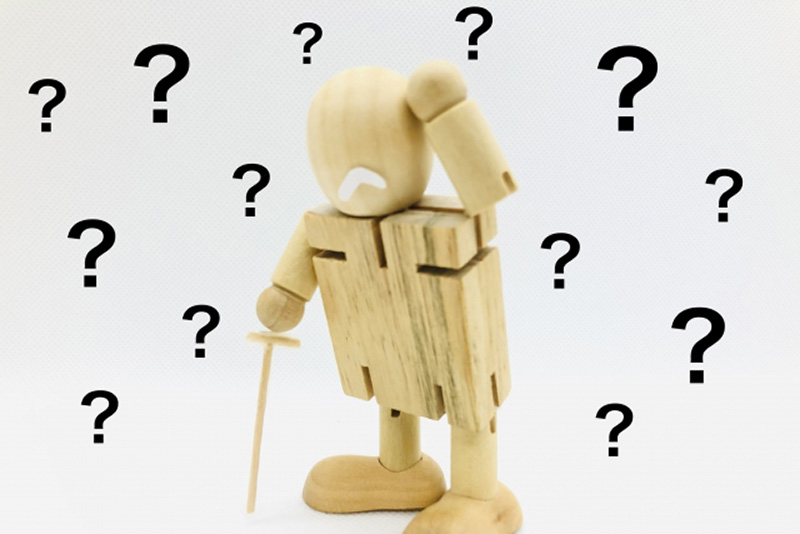
認知症とは、一度正常に発達した脳の機能が、さまざまな原因で持続的に低下し、日常生活や社会生活に支障をきたす状態を指します。 記憶障害だけでなく、判断力・理解力・言語能力・空間認知などの障害が組み合わさって現れます。 症状はゆっくりと進行することが多く、本人だけでなく、家族や周囲の生活にも影響を与えることがあります。
主な種類
認知症には複数のタイプがあり、原因や症状の特徴が異なります。
アルツハイマー型認知症
最も多いタイプで、脳にアミロイドβたんぱく質が蓄積し、神経細胞が徐々に壊れていきます。物忘れから始まり、徐々に判断力や日常動作にも影響します。
血管性認知症
脳梗塞や脳出血などによる脳の血流障害が原因で発症します。症状が段階的に進行するのが特徴で、麻痺や言語障害を伴うことがあります。
レビー小体型認知症
脳内にレビー小体という異常なたんぱく質がたまり、幻視や動作の緩慢、パーキンソン症状などを伴います。
前頭側頭型認知症
比較的若い年齢で発症することもあり、人格や行動の変化、言語の障害が目立ちます。
原因について

原因は多岐にわたります。アルツハイマー病やレビー小体病などの変性性疾患、脳梗塞や脳出血による脳血管障害のほか、頭部外傷や脳腫瘍、慢性硬膜下血腫、甲状腺機能低下症、ビタミン欠乏症など、適切な治療で改善が期待できる可逆性の認知症も存在します。
診断と検査
診断のためには、まず症状の経過や発症時期、生活への影響を丁寧に聞き取ります。そのうえで、記憶力や注意力、言語能力などを評価する神経心理検査を行います。さらにMRIやCTなどの画像検査で脳の萎縮や血流障害の有無を調べ、血液検査で代謝異常や内科的疾患を除外します。本人が症状を自覚しにくいことも多いため、家族や周囲からの観察記録が診断の重要な手がかりになります。
治療について

認知症は根本的な治療が難しいケースが多いものの、進行を遅らせたり症状を和らげる方法はあります。薬物療法では、アルツハイマー型認知症の進行を抑えるコリンエステラーゼ阻害薬や、中等度から重度の症状に用いられるNMDA拮抗薬が代表的です。攻撃性の亢進や問題行動等の周辺症状に対しては、必要に応じて抗精神病薬や抗うつ薬が併用されることもあります。薬物療法 以外にも、認知リハビリテーションや音楽療法、運動療法などの非薬物療法が有効な場合があります。家族族への介護指導や生活環境の調整も重要な対応策となります。
日常生活での注意点
認知症の方が安心して生活を続けるためには、転倒防止や火の管理、外出時の見守りといった安全対策が欠かせません。生活リズムを規則正しく保つことや、適度な運動、社会参加を促すことが進行予防につながります。栄養バランスの取れた食事や、感情的なやり取りを避けて穏やかな関係を保つことも大切です。
当院での対応について
当院では精神科としての立場から、認知症の診断と治療だけでなく、ご家族や介護者への支援にも力を入れています。丁寧な問診と検査による早期診断を行い、薬物療法と非薬物療法を組み合わせた包括的な支援を提供します。ご家族に対する介護相談や心理的サポートも充実させており、必要に応じて診断書や介護保険関連書類を即日発行することが可能です。平日は22時まで、土日祝は19時まで診療しているため、ご家族の生活スケジュールに合わせた受診ができます。またオンライン診療にも対応し、遠方や外出が難しい方にも安心してご利用いただけます。認知症は、適切な支援があれば自分らしい暮らしを続けられる病気です。私たちは、ご本人とご家族が安心して日々を過ごせるよう全力でサポートいたします。
