パニック障害について

「急に息ができなくなった」「心臓がバクバクして、このまま死ぬかと思った」「救急車を呼んだけれど、病院では異常なしと言われた」――こうした体験をきっかけに、同じような発作がまた起きるのではと強い不安を抱えるようになった方は、パニック障害の可能性があります。 身体的には何の異常もないのに、突然起こる激しい発作と、それに続く不安と回避行動。 この病気は、適切な治療と理解のある対応によって回復が期待できる精神疾患のひとつです。
パニック障害とは?
パニック障害とは、突然強い不安や恐怖感が起こり、動悸・息苦しさ・めまいなどの身体症状をともなう「パニック発作」を繰り返す病気です。 発作は、何の前触れもなく起きることが多く、はじめて経験する際には「このまま死ぬのでは」と感じるほどの激しい苦しさがあります。 その後、また発作が起こるのではないかという強い不安(予期不安)や、発作が起きた場所を避けるようになる(広場恐怖)など、生活の自由が大きく制限されてしまうことも少なくありません。
主な症状
パニック発作
以下のような症状が、10分以内に急激にピークに達するのが特徴です。 ・動悸・胸の圧迫感息苦しさ・過呼吸 ・めまい /ふらつき/気が遠くなる感じ ・発汗/手足の震え ・胃の不快感/吐き気 ・現実感の消失/自分が自分でない感じ 「このまま死ぬのでは」「気が狂いそう」といった強い恐怖 発作は通常数分から30分程度でおさまりますが、非常に強い恐怖感を伴うため、再発への不安(予期不安)が生じやすくなります。
予期不安・回避行動
一度パニック発作を経験すると、「またあの状態になったらどうしよう」という不安が常につきまとうようになります。 その結果、発作が起きそうな場所や状況(電車・エレベーターなど)を避けるようになることがあります。 これを繰り返すと、「外出ができない」「一人でいられない」「職場や学校に行けない」といった問題につながることもあります。
なぜ起こるのか?
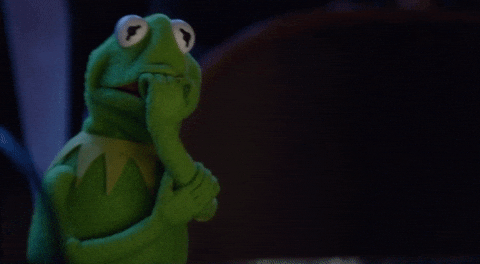
パニック障害の正確な原因はまだ完全には解明されていませんが、以下のような要因が関与すると考えられています。 ・脳内の不安・恐怖を調節する神経伝達物質(特にセロトニンやノルアドレナリン)のバランスの乱れ ・強いストレス、ライフイベント(職場・人間関係・災害・出産など) ・遺伝的素因や体質 ただし、はっきりしたストレスやトラウマがなくても発症することがあります。「気の持ちよう」や「性格の問題」ではなく、脳の反応が過敏になっている状態と捉えられます。
診断と治療
パニック障害の診断は、詳細な問診によって症状の出かた、持続時間、生活への影響などを確認することで行います。心電図や血液検査などで身体疾患を除外したうえで、診断されることが一般的です。 治療は、薬物療法と心理療法(認知行動療法)を中心としたアプローチが行われます。
薬物療法
症状の軽減を目的に、以下の薬剤が使用されます。 ・抗うつ薬(SSRI):セロトニンのバランスを整え、不安発作や予期不安を軽減します。 ・抗不安薬(ベンゾジアゼピン系):即効性があり、初期の強い不安を和らげるために使用されることがあります。➢長期使用には依存のリスクがあるため、慎重に扱われます。 薬の効果は数週間で現れ始め、半年〜1年程度の継続治療が標準的です。症状が落ち着けば、段階的に減薬していきます。
認知行動療法(CBT)
認知行動療法では、発作に対する過度な恐怖や「避けることが当然」という思考のクセを修正し、少しずつ不安に慣れていく訓練を行います。 ・「発作=死ぬ」という誤った認知を修正する ・少しずつ避けていた場所・状況に慣れていく(曝露療法) 心理療法は時間がかかる面もありますが、再発予防や薬に頼らない生活への移行に非常に有効です。
当院での対応について
当院では、パニック障害の症状に対して、丁寧な診察と必要な治療を通して、安心して生活を取り戻すサポートを行っています。 ・初診では、これまでの発作の経緯や不安の背景を丁寧にお聞きします ・必要に応じて、薬物療法を無理のない範囲でご提案します ・診断がついた場合には、休職や職場環境の調整に役立つ診断書を即日で発行することが可能です。 ・お仕事や家庭の都合で通院が難しい方には、オンライン診療にも対応しており、スマートフォンやパソコンからご相談いただけます。 ・外出や通院が難しい方も、夜間(平日22時まで)や土日祝の診療でサポートします 「また発作が起きるのでは」と不安な気持ちで日々を過ごしている方へ。その不安は治療によって少しずつ和らげていくことができます。ご自身のペースで、どうか一度ご相談ください。
