睡眠障害について
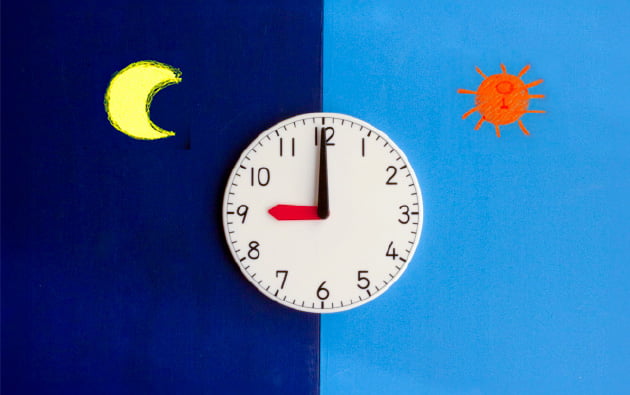
「夜、なかなか寝つけない」「何度も目が覚めてしまう」「朝早く目が覚めてしまう」――このような眠りの悩みを抱えていませんか? 睡眠は単なる休息ではなく、心身のバランスを保つために欠かせないものです。睡眠の質や時間が乱れると、集中力の低下やイライラ、体の不調にとどまらず、こころの健康にも大きく関わります。 今回は、精神科で扱う代表的な「睡眠障害」について、症状の特徴や治療法、よくある疑問点を交えてご紹介します。

睡眠障害の主なタイプ
「眠れない」「寝ても疲れが取れない」「日中眠くて困る」といった睡眠の悩みには、以下のようなタイプがあります。 ・不眠症 ・睡眠時無呼吸症候群 ・過眠症 ・概日リズム睡眠症候群 ・睡眠時随伴症 ・睡眠関連運動障害 ここでは、精神科領域で特に関係の深いこれらの睡眠障害をご紹介します。
不眠症(いわゆる「眠れない」状態)
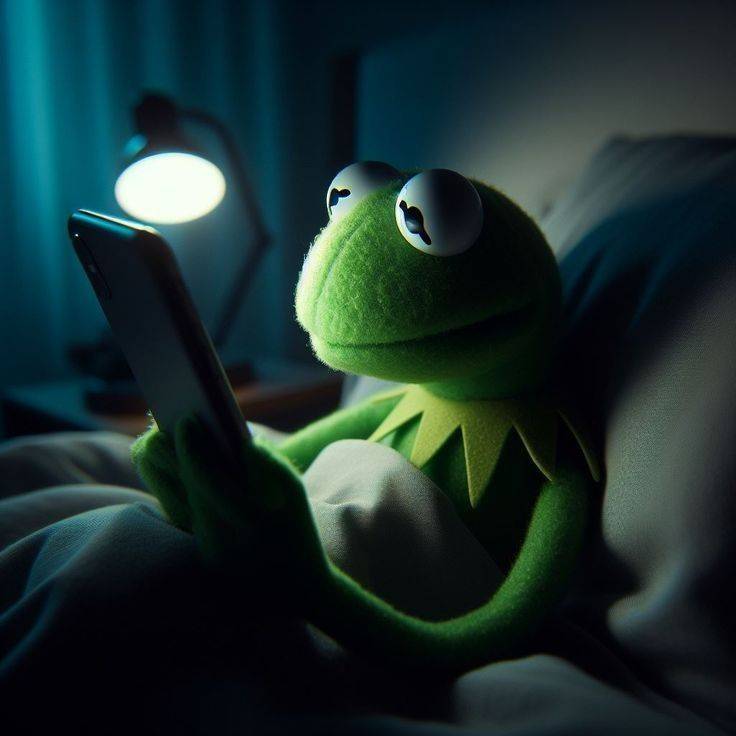
もっともよく見られる睡眠障害です。「寝つけない」「夜中に何度も目が覚める」「朝早く目が覚めてしまう」「眠った気がしない」といった症状が続き、日中の疲れや集中力低下に影響する状態を指します。心理的ストレスやうつ病、不安障害が背景にあることも多く、早めの対応が重要です。 治療の中心:生活習慣の見直しと必要に応じた薬物療法 薬物療法:非ベンゾジアゼピン系・メラトニン作動薬・オレキシン拮抗薬などを症状に応じて処方 補足:背景にうつ病や不安障害がある場合は、根本的な治療が優先されます
睡眠時無呼吸症候群(SAS)
睡眠中に呼吸が何度も止まることで、眠りが浅くなり、昼間に強い眠気が出る病気です。いびきや呼吸停止を家族に指摘されて気づくこともあります。肥満、中高年男性に多い傾向があり、放置すると高血圧や心疾患のリスクも高まります。睡眠外来や呼吸器内科での検査と治療が必要になります。 治療の中心:CPAP(シーパップ)療法=睡眠中に鼻に空気を送り、気道を開存させる治療 その他:減量、禁煙、飲酒制限、マウスピース、重症例では外科的治療 当院での対応:疑いがある場合は、睡眠外来・呼吸器内科など専門機関をご紹介します
過眠症(眠っても眠っても眠い)
夜に十分眠っているにもかかわらず、日中に強い眠気が続き、仕事中や運転中に眠ってしまうような状態です。代表的なものに「ナルコレプシー(睡眠発作・脱力発作を伴う)」や「特発性過眠症」があります。単なる疲労や生活リズムの乱れと見分けにくいため、専門的な評価が必要です。 治療の中心:日中の眠気を軽減する薬剤(モダフィニル、ピトリサント等) 生活面:短時間の昼寝や睡眠スケジュールの調整が有効

概日リズム睡眠障害(体内時計のずれ)
体内時計(概日リズム)が実際の社会生活の時間とずれてしまうことで起きる障害です。たとえば、「眠れるのが深夜2〜3時以降でないと無理」「朝起きられず学校や仕事に行けない」といった症状が出ます。若年層に多く、単なる夜更かしや怠けとは異なる病気です。光療法や生活調整、薬物療法が治療の柱となります。 治療の中心:体内時計の調整 ・朝の強い光(光療法) ・メラトニン作動薬(ロゼレムなど)の適切な時間での投与 生活指導:就寝・起床時刻の固定、学校・職場との調整が鍵になります
睡眠時随伴症(パラソムニア)
睡眠中に起きる異常な行動や体の反応を指します。寝ぼけて歩き回る「夢遊病」、うなされるように叫ぶ「夜驚症」、恐怖感のある夢で目覚める「悪夢障害」などがあります。子どもに多く見られますが、大人でもストレスや睡眠不足、アルコールの影響で出現することがあります。 治療の中心:安全確保と原因の除去(ストレス、不眠、アルコール等) 薬物療法:症状が強い場合は、ベンゾジアゼピン系などを短期間使用 子どもに多いタイプ:成長とともに自然に軽快するケースもあります

睡眠関連運動障害
眠る前に脚がムズムズして眠れない「むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)」や、睡眠中に脚がピクッと動いて目が覚める「周期性四肢運動障害」などがあります。鉄分の不足や神経系の異常が関係することがあり、内科的な評価や治療が必要なケースもあります。 むずむず脚症候群(RLS):ドパミン作動薬や鉄分補充が基本 周期性四肢運動障害:睡眠中の動きを軽減する薬剤(クロナゼパムなど)
当院の診療について
当院では、睡眠障害に関するお悩みについて、医師と看護師が一人ひとりの症状に合わせて丁寧に対応いたします。必要に応じて他機関との連携も可能です。 ・平日 11:00〜22:00/土日祝 11:00〜19:00まで診療 ・仕事帰り、学校帰りにも通いやすい時間帯 ・診断がついた場合には、休職や職場環境の調整に役立つ診断書を即日で発行することが可能です。 ・お仕事や家庭の都合で通院が難しい方には、オンライン診療にも対応しており、スマートフォンやパソコンからご相談いただけます。 ・状況に応じた薬の処方と、生活改善へのサポート
