てんかんについて

てんかんというと、「急に倒れる病気」「子どもの頃の病気」といったイメージを持たれることが多いかもしれません。 しかし実際には、年齢にかかわらず発症しうる、脳の慢性的な状態に基づく神経疾患です。 日本では約100人に1人がてんかんを有していると言われており、決して珍しい病気ではありません。 また、発作を繰り返す病気ではありますが、適切な治療によって約7割の方が発作を十分に抑えられることもわかっています。

てんかんとは?
てんかんとは、脳の神経細胞の異常な電気的興奮が繰り返し起こることで、意識障害やけいれんなどの発作が起こる状態を指します。 脳は電気信号で情報をやりとりしていますが、その信号の流れが一時的に異常になると、突然の動きや意識の変化などが起こります。 これが「てんかん発作」です。
発作の種類
てんかんの発作には、さまざまなタイプがあります。
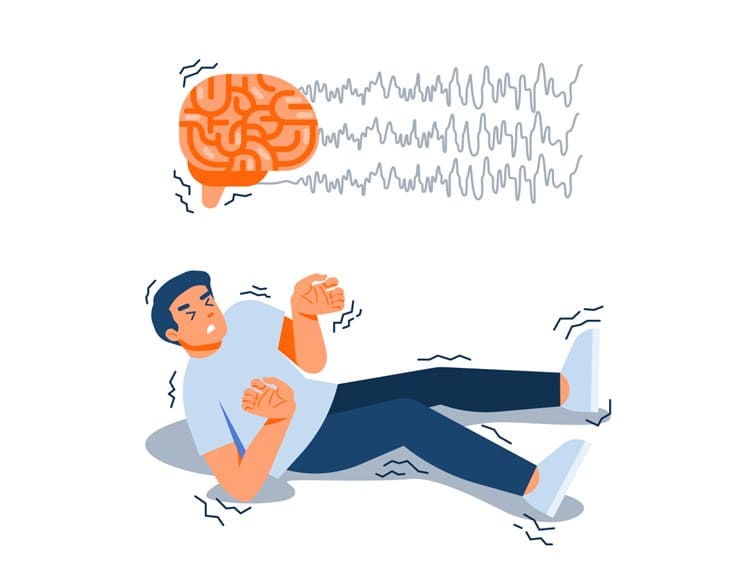
全般発作
脳全体が一度に興奮するタイプで、典型的な「全身けいれん」や意識消失を伴います。 ・強直間代発作(いわゆる「倒れてけいれん」する発作) ・欠神発作(数秒間、急にぼんやりして反応がなくなる) ・ミオクローヌス発作(体の一部がピクッと急に動く)
部分発作(焦点発作)
脳の一部から始まる発作で、意識がある場合とない場合があります。 ・意識は保たれているが、手が勝手に動いたり、感覚が変わる ・意識がぼんやりし、奇妙な行動(口をもぐもぐ動かす、徘徊するなど)をとる てんかん=「大きなけいれん発作」というイメージが強いですが、実際には目立たない・気づかれにくいタイプの発作も少なくありません。
原因について
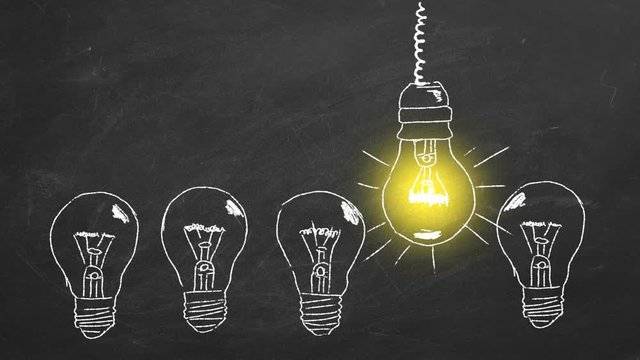
てんかんの原因は大きく以下のように分けられます。 ・特発性(原因不明):脳の構造には問題がなく、遺伝的な体質が関係することもある ・症候性:脳卒中、頭部外傷、脳腫瘍、先天異常などが原因 ・構造的・代謝性:特定の脳の構造異常や代謝異常が関連 特に成人や高齢者では、脳卒中後の後遺症としててんかんが発症するケースも増えています。
診断と検査

てんかんの診断には、以下のような方法が用いられます。 問診(発作の様子、時間帯、頻度、前ぶれなど) 脳波検査(異常な電気的活動を記録) MRIやCTによる脳の構造評価 ご本人が発作の記憶をはっきり覚えていないことも多いため、周囲の方の観察記録や動画が診断に役立つこともあります。
治療について
てんかん治療の中心は、抗てんかん薬による発作のコントロールです。
薬物療法
発作のタイプに応じて薬を選び、1日1〜2回の内服を継続することで発作の予防を目指します。主な抗てんかん薬には、以下のようなものがあります。 ・バルプロ酸(デパケンなど):広い発作タイプに対応、気分の安定にも有効 ・ラモトリギン(ラミクタール):部分発作やうつ症状を伴う方に適している ・レベチラセタム(イーケプラ):副作用が比較的少なく、処方されやすい薬の一つ 薬の種類や量は個人の体質や生活スタイルに応じて調整していきます。 副作用としては、眠気・ふらつき・皮膚症状などが挙げられますが、医師と相談しながら対処することで、継続が可能なケースが多いです。
その他の治療
・難治性てんかんに対しては、外科的治療やVNS(迷走神経刺激療法)が検討されることもあります ・食事療法(ケトン食など)は、主に小児の難治例で用いられます
日常生活での注意点

てんかんのある方は、以下のような点に注意することで、発作の誘因を減らすことができます。 睡眠不足を避ける 過度の飲酒や急な生活リズムの変化を控える ストレス管理 入浴・水泳・高所作業などの際は、状況に応じた安全対策を 薬の服用を自己判断で中断すると、発作が再発・悪化するリスクがあるため、必ず医師の指示のもとで調整してください。
当院での対応について
当院では、精神科としての立場から、てんかんの診断・治療に加え、精神的な不安や併存疾患の管理にも重点を置いた診療を行っています。 ・不安や抑うつ症状、社会生活の不安を抱える方への丁寧な問診と相談 ・薬物療法の調整や、日常生活へのアドバイスも含めた包括的な支援 ・必要に応じて、診断書や通院証明書の即日発行も可能 ・平日22時・土日祝19時まで診療のため、お仕事や通学と両立しながらの通院も可能です ・お仕事や家庭の都合で通院が難しい方には、オンライン診療にも対応しており、スマートフォンやパソコンからご相談いただけます。 てんかんは、「発作さえなければ普通に生活できる病気」です。 ご本人も、ご家族も、不安を抱えすぎず、安定した日常を目指して一歩ずつ前に進めるよう、全力でサポートいたします。
