社交不安障害(SAD)について

「人前で話すと頭が真っ白になる」「視線が気になって外食できない」「緊張で声が震え、動悸が止まらない」 このような強い不安が日常生活に支障をきたしている場合、社交不安障害(SAD:Social Anxiety Disorder)の可能性があります。 単なる「あがり症」や「人見知り」とは異なり、社交不安障害は医療による治療が必要となる精神疾患のひとつです。 しかし、適切な支援や治療によって改善が見込める病気でもあります。

社交不安障害とは?
社交不安障害は、他人からの注目を浴びるような場面に対して、過剰な不安や恐怖を感じてしまう疾患です。 特徴的なのは、以下のような状況で強い苦痛が生じることです。 •人前で話す、発表する •初対面の人と会話する •注目される状況(会議、食事、電話など) •書類に署名する場面(手が震える)など こうした場面を「避ける」ことで一時的に安心できても、生活範囲が狭まり、仕事や学業、人間関係に深刻な影響が及ぶことがあります。
主な症状
社交不安障害の症状は、身体面・心理面・行動面にわたります。 ● 身体的症状 •動悸、震え、発汗、声の震え •顔の紅潮、吐き気、腹痛 •息苦しさやめまい ● 精神的症状 •「恥をかくのでは」「失敗したらどうしよう」という強い予期不安 •自分の様子を常に気にしてしまう(自己注目) •人の視線や評価が極端に怖い ● 行動の変化 •学校や職場を休む、退職する •外食を避ける、人との会話を避ける •恥をかかないように完璧に準備しようとして疲れ切ってしまう これらの症状が6か月以上続き、明らかに日常生活に支障をきたしている場合、社交不安障害と診断される可能性があります。

診断について
診断は、症状の持続期間や日常生活への影響の程度、他の疾患との鑑別などを含めて、問診を中心に行います。 他の不安障害やうつ病と併存することもあるため、丁寧な聞き取りが重要です。

治療について
症状の強さや生活への影響に応じて、以下のような薬を使用します。 •SSRI:不安症状を和らげる。効果が現れるまで2〜4週間ほどかかるが、長期的に安定しやすい •抗不安薬(ベンゾジアゼピン系):即効性があるが、依存性や眠気に注意し、短期間に限定して使用 •β遮断薬:プレゼンや面接前など、一時的に身体症状(動悸、震え)を抑えるために用いることがある 薬は症状の程度に応じて調整され、日常生活を支える一助として使用されます。 ● 認知行動療法(CBT) 社交不安に有効とされる代表的な精神療法です。 「自分は見られている」「失敗=評価が下がる」といった過度な思い込み(認知)に働きかけ、それに基づく回避行動を少しずつ修正していく方法です。
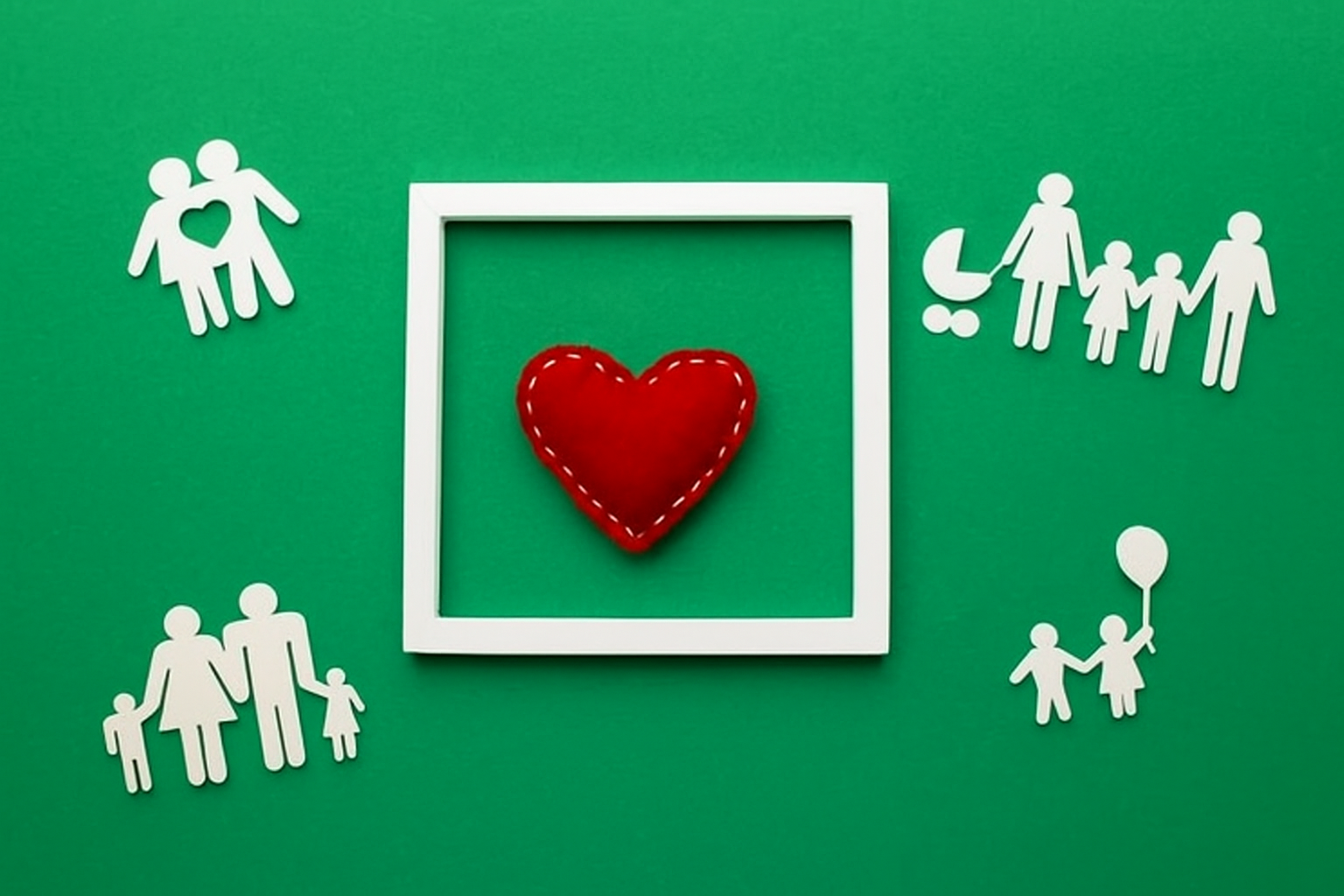
当院での対応について
当院では、社交不安障害の診療において、ご本人の不安や生活上の困難に丁寧に寄り添うことを大切にしています。 •発症の背景や困っている場面について丁寧にヒアリングを行い、診断と治療方針をご提案します •ご希望に応じて、就学・就労に関する配慮事項を含む診断書の即日発行も可能です •薬の効果・副作用を見ながら慎重に調整し、再診も柔軟に対応します •お仕事や家庭の都合で通院が難しい方には、オンライン診療にも対応しており、スマートフォンやパソコンからご相談いただけます。 •平日22時、土日祝日19時まで診療しており、人目を避けたい方でも通いやすい時間帯での予約が可能です 「恥ずかしがり屋だから」「気にしすぎる性格だから」と、自分を責め続けてきた方も少なくありません。 でも、社交不安障害は“治療できる”病気です。不安のない、のびのびとした日常を取り戻すために、一緒に取り組んでいきましょう。
