自閉症スペクトラム障害(ASD)について

「相手の気持ちがうまく読み取れない」「こだわりが強くて周囲とトラブルになりやすい」「話し方や空気の読み方が変わっていると言われる」―― そうした特性が日常生活や人間関係で困りごとにつながっている場合、自閉症スペクトラム障害(ASD)の可能性があります。 ASDは、「社会的なやりとり」「コミュニケーション」「柔軟な思考・行動」に特性がある発達障害のひとつです。 本人の努力不足や性格の問題ではなく、生まれつきの脳の特性であるため、特性に合った理解と支援を行うことで、生活が安定しやすくなります。
ASDとは?
ASD(Autism Spectrum Disorder)は、以下のような特性を持つ神経発達症です。 ・対人関係の難しさ(人との距離感がつかみにくい、表情や意図が読み取りにくい) ・言語や非言語コミュニケーションの特性(言葉の裏の意味をとらえるのが苦手、冗談や暗黙のルールがわかりにくい) ・強いこだわりや興味の偏り(特定の物事への熱中、ルールや手順の変化への抵抗) ・感覚の過敏・鈍感(音・におい・触感などへの極端な敏感さや無反応) ASDは「スペクトラム(連続体)」という言葉の通り、症状の強さや表れ方に幅があり、人によって困りごとは異なります。 知的な遅れを伴う方もいれば、知的能力は高いが対人関係に苦手さを抱える方もいます。
子どもと大人での現れ方の違い
子どもの場合
・友達とうまく遊べない ・こだわりが強く、生活が一辺倒になる ・会話が一方通行、空気が読めないと指摘される ・大きな音やにおいを極端に嫌がる ・感情表現が乏しい、または逆に極端

大人の場合
・空気が読めず、職場や家庭で人間関係がうまくいかない ・柔軟な対応が苦手で、仕事でミスや摩擦が起こりやすい ・生活の変化に強いストレスを感じやすい ・自己評価が低く、うつや不安症状を伴うことがある 大人のASDは、長年「生きづらさ」の正体がわからないまま過ごしてきた方が、うつや不安などをきっかけに受診して発覚することもあります。
診断について
ASDは、問診や生育歴、日常生活での困りごとなどを丁寧に確認した上で診断されます。 必要に応じて、心理検査(発達検査や知能検査など)を行う場合もあります。 ・「本人の特性が、社会生活にどのように影響しているか」 ・「どのような場面で困りごとが生じているか」 これらを総合的に評価し、他の疾患との違いも見極めながら診断します。
治療と支援の考え方
ASDは、症状を完全になくすことを目的とするものではなく、特性を理解したうえで日常生活を送りやすくすることが治療の主眼です。

環境調整
・負担のかかる環境や人間関係を見直し、ストレスを減らす ・得意な形で情報を整理しやすいよう、視覚的支援やルール化を導入 ・変化への不安を和らげるための「見通し」の提示
薬物療法
ASDそのものに対する治療薬はありませんが、併存しやすい症状(不安、抑うつ、睡眠障害、過敏性)に対して薬物療法を行うことがあります。 ・不安や緊張が強い場合 → 抗不安薬 ・抑うつ傾向がある場合 → 抗うつ薬(SSRIなど) ・睡眠障害 → メラトニン受容体作動薬など 薬は状態に応じて最小限にとどめ、副作用にも注意しながら慎重に使用します。
当院での対応について
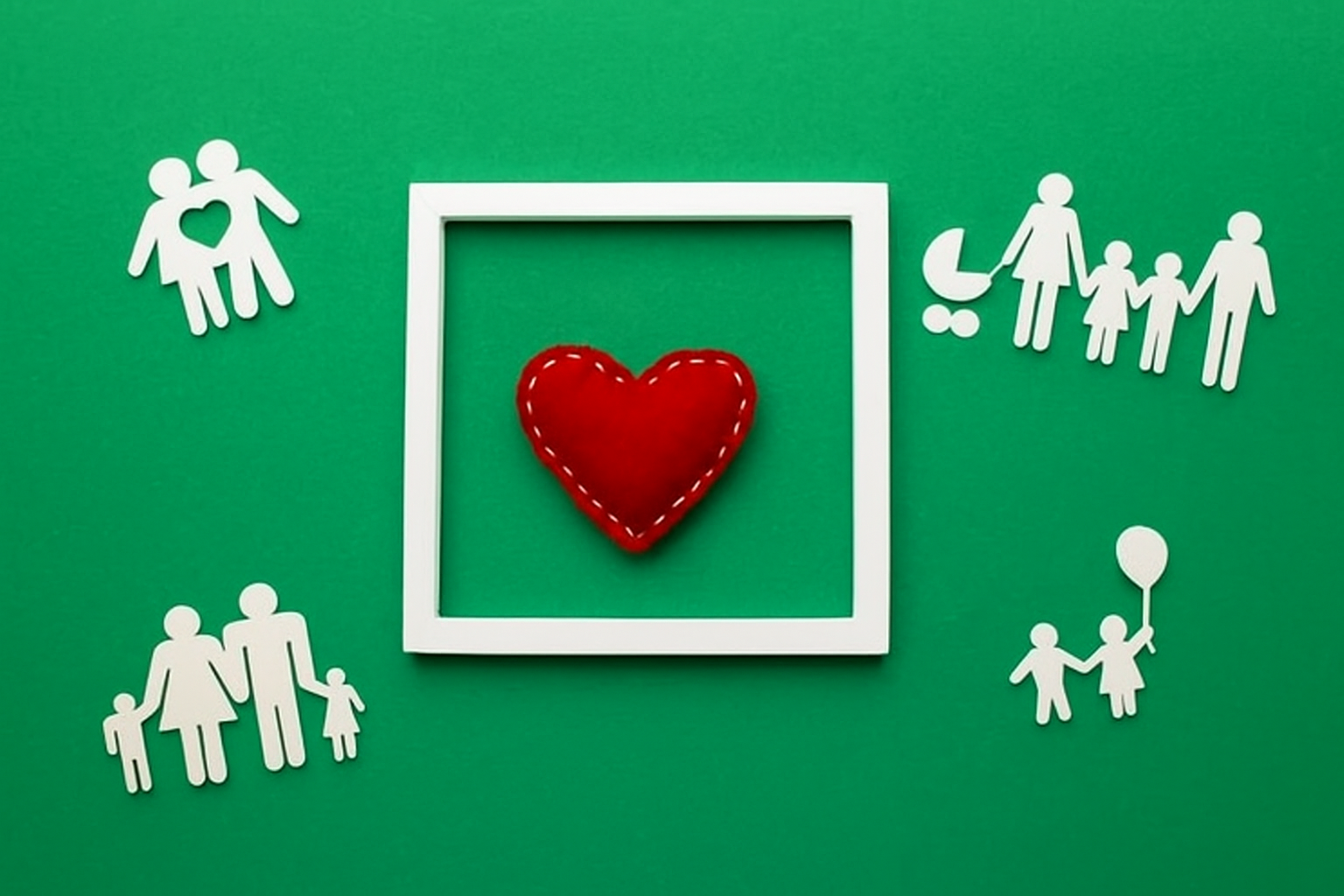
当院では、自閉症スペクトラムの診療において、「ひとりひとりの困りごと」に丁寧に向き合い、本人のペースに合わせた支援を行っています。 ・初診時に、日常生活や人間関係の中での具体的な困難を詳しくうかがいます ・ご希望があれば、診断書や職場・学校への配慮のための文書も即日発行できる場合があります ・精神的な負担が大きい場合には、症状に応じた薬物療法でのサポートも行います ・平日は22時まで、土日祝日は19時まで診療しており、ライフスタイルに合わせた通院が可能です ・お仕事や家庭の都合で通院が難しい方には、オンライン診療にも対応しており、スマートフォンやパソコンからご相談いただけます。 「人と違う自分」を責めたり、合わせようとして疲れ切ってしまう前に。 特性を知ることは、自分らしく生きるための第一歩です。 ご本人だけでなく、ご家族からのご相談も受け付けていますので、どうぞ安心してご連絡ください。
